本記事では前述のベリー貨物に焦点を当てていきます。
ベリー貨物(Belly Cargo)とは航空機の床下貨物スペースで運ぶ、航空貨物のことを指します。
旅客機、貨物機ともに一般的にあります。
なかなか日の目を浴びることはないのですが、今回のコロナショックでベリー貨物が一躍注目を浴びたことは言うまでもありません。詳細は、前述の記事で記載しましたが、旅客便の運航がコロナによって制限されたことと、巣ごもり需要等のコロナ期特有の特需で、航空貨物の単価が高騰しました。
その結果、旅客の激減で喘ぐ航空各社は航空貨物部門の強化に全力を挙げております。国内でもANAやJALはもちろんのこと、LCCのピーチやジェットスタージャパンも旅客機を使って貨物輸送を行っております。なぜ貨物機を持たないJALやLCCが貨物事業を行うことができるのかというと、ベリー貨物を取り扱っているからです。
ベリー貨物をコンテナで搭載する方法と、バラ積みで搭載する方法の、2種類の方法があります。
1)コンテナで搭載
ベリー貨物コンテナで搭載することができるのはワイドボディ機と一部のナローボディ機(A320シリーズ)に限定されます。コンテナのための十分なスペースがないB737やB757といったナローボディ機には搭載できません。コンテナ搭載スペースは一般に、航空機の前方と後方の2か所に分かれます。コンテナは作業効率が良いため、より多くの荷物を効率的に搭載することができます。
航空コンテナには規格があり、機体サイズによって最適なコンテナが搭載されます。
2)バラ積み搭載(貨物室レイアウト図の灰色部分)
コンテナを搭載できないB737といったナローボディ機は、バラ積みで荷物を搭載しないといけません。またワイドボディ機もバルクスペースという貨物室があり、そちらに主に乗客の手荷物をバラ積みで搭載することが可能です。旅客数が多い大型機ではバルクスペースだけでは乗客の手荷物をさばききれないため、コンテナにも手荷物を搭載するのが一般的です。旅客が多い便では、1/3程度のコンテナは手荷物で埋まってしまいます。またコロナ禍では座席やオーバーヘッドビン(天井の手荷物スペース)にもバラ積みで貨物を搭載するオペレーションも一部採られております。
バラ積みは効率が悪いため、基本は乗客の荷物のみを搭載します。コロナ禍では、バラ積みでも有償貨物の搭載が行われたようです。コロナ禍ではコンテナのキャパシティが大きなメリットになりました。
国際線では旅客機を使った貨物臨時便が多く設定されました。特に多くのUA便やAA便、AC便がアメリカから乗客を乗せずに成田を経由して、中国を中心とするアジア都市へ多数の臨時便を運航していた様子は圧巻であり、異様な光景でした。そしてそれらのほとんどは、B777やB787を使って運航されました。下表は各機種のコンテナ搭載可能量を示しております。

例えば、大型のB777-300ERは44個のLD-3コンテナを一度に搭載出来、構造上は65トンの航空貨物を搭載可能です。これは中型貨物専用機のB767Fのペイロード(有償搭載量)を上回るキャパシティです。また旧大型機の747より多くのコンテナを搭載することが可能です。同シリーズの貨物専用機B777-200Fは102トンまで搭載可能ですが、それの3/5程度まで搭載できることは驚きです。
ちなみにアメリカン航空が777-300ERに搭載した最大の貨物量は、52トンとのことです。
通常の旅客便ですと、乗客の重量や手荷物、さらに滑走路の長さや航続距離、ジェット気流等の気象条件といった制限を考慮し、最大構造ペイロード(Gross structural payload)には到底及ばない27トン程度の有償貨物量に留まります。それでも小型貨物専用機のB737F(ペイロード16トン)を上回る積載能力を有しております。
加えて多くの旅客便は毎日運航されているため、1週間当たりの輸送能力は単純計算で189トンになります。これはジャンボジェット貨物機 B747-8Fのペイロード140トンを上回ります。
比較的軽い旅客機は、航続距離で貨物機を上回るという利点もあります。特にアジアからの欧州便や北米便(特に東海岸路線)は、貨物機である場合アンカレッジ等の中継地で給油して運航されることが多いですが、旅客機のベリー貨物便であれば直行で結ぶことが可能です。
コロナ禍では旅客機を使った臨時貨物便が運航されており、これらは乗客を乗せない状態で運航しております。また客室キャビンの座席やオーバーヘッドビン(天井の手荷物スペース)に貨物を手作業で搭載して運航しているケースも多々あります。極端なケースですと、座席を取り払って、重量やスペースを有効利用し、最大70トンの貨物を運んだB777旅客型のプレイター(Preighter)も存在するとのことです(客室を利用した場合、65トンを上回る貨物の搭載が可能)。ただし、客室を使った運航はバラ積みで作業効率が悪いため、すべてがその運航形態をとっているわけではありません(とはいえ、航空各社は一時的な深刻な人員余剰と経営危機に直面しており、作業効率を言っている余裕はない状況ですが)。
コロナ禍で搭乗率が極端に低い国際便がなぜ運航されているか疑問に感じる方も多いと思いますが、これらは乗客よりもベリー部分の有償貨物の収益をターゲットに運航しております。搭乗率が低ければ、それだけ多くの有償貨物を輸送することが可能で、路線で黒字化することも可能です。こうした状況であれば、旅客便であっても多数の有償貨物を輸送することが可能です。
このような努力を積み重ね、航空貨物単価の高騰と貨物供給の増強により、JALやANAは航空貨物収益をコロナ前と比較し、倍増させており、コロナ禍の貴重な収入源となっております。
こうしたことから、普段であっても旅客便によるベリー貨物は多くの利点があり、エアバスは56%の航空貨物はベリー貨物として輸送されるとの見通しを示しております。ベリー貨物は基本コンテナによる輸送に制限され、貨物機のように大型で長大な貨物は運べないというデメリットもありますが、実際には小型の貨物品目が中心であるため、90%の荷物はベリー貨物で運ぶことが可能です。
Eコマースの拡大や半導体等の貴重貨物の需要拡大で、航空貨物需要はコロナが落ち着いてもさらに増加していくことが見込まれます。今後はますますベリー貨物の重要性が増大していき、エアラインや航空機メーカーはそれに対応することが求められるでしょう。
例えばB737は2回のMAXの事故で構造的な問題があることが明らかになり、次世代機はデザインの完全な刷新が求められるでしょう。その際はA320と同様にコンテナ搭載が可能なデザインになると著者は見ております。またLCCを含むエアラインは、今後は航空事業の多様化のため航空貨物事業の拡充をしていく可能性があると思います。

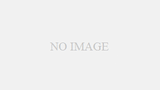
コメント